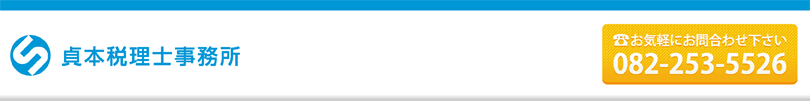簿外経費の立証責任は、納税者側
建設会社がコンサルタントに支払った業務報酬の損金算入可否が争われた事案で、東京地裁は、納税義務者が簿外経費の損金算入を主張する場合は、その立証責任は納税義務者側にあるとし、立証できなければ損金算入不可と判断しました(令和3年12月23日判決)。山口県で土木建設業を営むX社は、不動産ブローカー甲の紹介により大手住宅販売会社A社のマンション6棟の建設施工を受注。その見返りとして、それぞれの工事ごとに甲に対して数千万円のコンサルタント業務費を支払いました。しかし、平成25年契約の工事においてはコンサルタント契約の相手方を甲ではなくN社とし、平成26年契約の工事では同様にT社としました。X社はそれぞれのコンサルタント業務費を損金に算入して申告しましたが、税務署は、これらは架空経費であり、損金算入はできないとして否認しました。
X社は裁判で、甲がN社、T社の代理人であると認識していたこと、支払先の名義はどうあれ、甲の役務提供とその対価の支払の事実は変わらないことから、損金に算入すべきと主張しました。東京地裁は、本件のような帳簿書類と異なる必要経費、すなわち簿外経費の主張の場合は、納税義務者側が必要経費として支出した金額、支払年月日、支払先、支払内容等の事実や業務との関連性について主張立証すべきであり、それがない限りその経費を損金に算入することはできないと判断しました。X社の請求を棄却しました。
通常、税務調査等においては、立証責任は税務署側にあるものですが、このような簿外経費については、納税者側にあるとしたものです。
令和4年7月
外国子会社から受けた配当金を益金不算入の否認
外国子会社から受けた配当金を益金に算入せずに法人税の申告を行ったところ、制度の対象となる外国子会社には該当しないとして否認されました。大阪地裁は、株式の保有割合が25%に達していないとして、納税者の請求を却下しました(令和3年9月28日判決)。X社はカナダ子会社A社から約6億円の配当金を受けました。X社は法人税法23条の2第1項の「外国子会社配当益金不算入制度」を適用し、配当金の95%を益金不算入として法人税の申告を行いました。課税庁は、A社が本税制における「外国子会社」には該当しないとして否認しました。X社はこの処分を不服として訴訟を提起しました。
法人税法施行令22条の4第1項2号は、「外国法人の発行済株式のうち議決権のある株式の数又は金額のうちに占める保有株式の割合が25%以上」という要件を規定しているが、この要件に該当するか否かが争われました。X社は議決権割合の26%を保有しているため、制度上の外国子会社に該当すると主張しました。
大阪地裁は、政令で定める「議決権のある株式の金額」とは当然に「株式の額面金額」を意味するが、X社が保有する株式は議決権があるものの額面株式ではないため、X社の「議決権のある株式の金額」は存在しないと指摘しました。結果として、A社は制度上の外国子会社には該当しないと判断し、X社の請求を斥けました。
もっと分かりやすい要件としていただきたいです。
令和4年7月
取締役の債務肩代わりで債務免除を受けた会社にも第二次納税義務
取締役が会社の債務を肩代わりし、その求償債権を放棄した事案で、取締役自身の滞納国税に係る第二次納税義務が会社側に課されました。東京地裁は、求償権の放棄は会社に「異常な利益」を与えたことになるとして、課税処分を適法と認めました(令和2年11月6日判決)。請求人X社の代表取締役Aと取締役Bは平成27年、個人資産を売却した上で、X社の負債約4,000万円を代位弁済し、X社からの借入金約1,000万円と相殺した残額の約3,000万円の求償債権を放棄しました。平成29年に課税庁は、AとBが所得税と相続税等計約3,000万円を滞納していたことから、両名が債務免除したX社に対し、国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に基づき、両名の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分を行いました。X社はこの処分を不服として提訴しました。
裁判でX社は、国税徴収法39条の「無償譲渡等」とは第三者に「異常な利益」を与えることを指しますが、本件は経営者責任の履行として代位弁済・債務免除を行ったもので、必要かつ合理的な理由に基づくものであるから、第二次納税義務の対象とはならないと主張しました。これについて東京地裁は、「経営者責任とは法的責任ではなく、あくまで社会的責任である」と指摘した上で、本件債務免除が企業の再生手続の中で必要なものであったとしても、「異常な利益」に当たらないということはできないと判断し、X社の請求を棄却しました。
この第二次納税義務は、あまり身近ではないため、うっかり気づかないことが多いと思います。考え方や解釈の余地があるとは思いますが、その人間のすべての行動を把握するのは、不可能です。
令和3年5月
販売用マンションからの賃貸収入も課税売上のみ対応仕入と判断
消費税不動産業者が販売用に仕入れたマンションの購入額を、仕入税額控除の計算上、「課税売上げのみに対応する課税仕入れ」に区分して計算・申告したところ、販売収入だけでなく賃料収入も目的だったとして「共通対応課税仕入れ」に区分すべき――として否認されました。これを巡って争われた事案で、東京地裁は納税者の主張を認容し、全額を課税対応仕入れと判断しました(令和2年9月3日判決)。
不動産業を営むX社は、中古マンションを仕入れ、リノベーションやリーシングなどを施してバリューアップしたうえで、富裕層向けの投資用商品として販売していました。X社は平成29年3月期までの3課税期間、マンションの仕入金額を「課税対応仕入れ」に対応するものとしたうえで仕入税額控除(個別対応方式)の計算を行い申告したところ、課税庁は「マンションからは賃料収入もあり、将来の転売だけでなく住宅の貸付けも目的とされていたので、共通対応課税仕入れに区分すべき」として更正処分等を行いました。X社はこれを不服として提訴しました。
東京地裁は、課税仕入れの用途区分については実際にどのような取引が行われたかを見るまでもなく、どのような目的で行われたかにより判定すべきとしたうえで、X社の行ったリーシングなどは将来に収益不動産を売却するために行われたことは明白であり、これを共通対応仕入れと解することは経済実態と著しく乖離していると指摘しました。賃料収入はあくまで副産物であると判断し、X社の主張を全面的に認め、課税処分を取り消しました。
なかなか、判断の難しい事例です。納税者の内心の意図を推測しています。
消費税は、内心の意図を推測したような税制改正が行われることもあると思います。偶然のケースまで含んでいます。
令和3年4月
令和3年度税制改正 所得拡大促進税制について、中小企業は適用しやすい仕組みに代わります
中小企業が適用できる所得拡大促進税制は、令和3年度税制改正により、制度創設当初における前年度の雇用者給与等の総額と比較して一定割合増加した場合に税額控除ができる制度に戻ります。前期からの継続雇用者の給与等支給額を比較していた改正前の制度では継続雇用者を的確に抽出して判定するのに手間がかかり、適用機会も狭められていましたが、今回の改正により中小企業は適用しやすい仕組みに代わります。適用判断を誤り、税理士損害賠償事故になるケースも少なからずあったため、税理士にとっても朗報です。ところで所得拡大促進税制について、大企業は、令和3年度改正により、新規雇用者給与等支給額の増加割合で判定する人材確保等促進税制へと代わり、中小企業の制度とはその趣旨が異なるものとなります。もちろん、中小企業が大企業向けの税制を選択してもかまいませんが、適用しやすくなるのは圧倒的に令和3年度改正による中小企業の制度のほうです。
改正前後を新旧比較すると、1点目は継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上とする要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合によって判定することになります(税額控除率は15%)。
同様に税額控除率が10%上乗せされて25%となる要件についても、前年度の雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上となればOKです。加えて、教育訓練費要件を満たすか、令和3年度改正のM&A税制の対象となる場合には、経営力向上の証明があれば上乗せ措置が受けられます。
この制度は、中小企業にとってありがたいものです。大いに活用したいですね。
令和3年4月
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.