税理士日記
税理士日記
10月1日にインボイス登録通知が未達の場合
2023/09/13 11:56:17
10月1日にインボイス登録通知が未達の場合の対応
国税庁は新たに「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を特設サイトに掲載し、制度開始の10月1日に登録通知が間に合わなかった場合について、売手と買手のそれぞれの対応を示し、注意喚起しています。インボイスの登録通知は、事業者から申請があってから、処理期間の短いe−Taによる申請でも1か月を要し、9月に入ってからの申請となると制度導入の10月1日に間に合わない可能性が高い状況です。このため、国税庁は今回、10月1日までに登録通知書が届かなかった対応を示すことにしたものです。
それによると、売手側は(1)事前に遅れる旨を伝えて通知後にインボイス交付(2)番号のない請求書を交付し(通知後)インボイスを交付し直す、(3)番号のない請求書との関連性を明確にして登録番号を書類やメールでお知らせ――の3パターンです。取引相手が不特定多数の小売店などは(1)から(3)が困難なため、「インボイスの交付が遅れる」旨をホームページや店頭に掲示し、(通知後)ホームページ上で「弊社の登録番号はT1234・・・・です。令和5年10月1日から●月●日までのレシートをお持ちの方は、仕入税額控除の際に当ページを印刷する」など、レシートと一緒に保存する方法でもOKです。
買手側からすると、売手から登録番号の連絡を受ける前に申告期限を迎えた場合にどうするかですが、国税庁は、売手から登録を受ける旨を知らされていれば、申告期限後に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存しておけば、登録番号のない請求書に記載された金額で仕入税額控除しても構わないとしています。
未だインボイス登録を迷っておられる方が多数おられます。高齢の方には、制度の理解も難しいと言われる方もいらっしゃいました。
ふるさと納税に関する現況調査
2023/08/31 11:25:03
ふるさと納税に関する現況調査
総務省からこのほど公表された「ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、令和4年度中に地方団体が受け入れたふるさと納税額は約9,654億円にのぼり、過去最高を3年連続で更新したことが分かりました。ふるさと納税を受け入れた件数も5,184万件余りを数え、過去最高を更新しています。受入件数はふるさと納税制度が導入された平成20年度以来15年連続で増加しています。
令和4年度中にふるさと納税の受入額が最も多かった都道府県は、前年度に続き、北海道で約1,452億円でした。次いで福岡県の約550億円、宮崎県の約466億円、鹿児島県の約424億円、佐賀県の約416億円の順です。北海道は別格として、九州勢の健闘ぶりが目覚ましいです。これを市町村別に見ると、1位は宮崎県の都城市の約195億円、2位は北海道の紋別市の約194億円で、前年度の1位と2位が逆転しています。3位は北海道の根室市の約176億円、4位が同じく北海道の白糠町の148億円で続きます。大阪府の泉佐野市は受入額約137億円で昨年と同様に5位を維持しました。
ふるさと納税を受け入れた地方団体がある一方で、その裏返しとして住民税が控除となった地方団体があります。この住民税控除額が多い都道府県は、順に東京都の約1,689億円、神奈川県の約707億円、大阪府の約549億円、愛知県の約491億円、埼玉県の約390億円となっており、前年度と順位は変わりませんが、控除額はそれぞれ増加しています。
ふるさと納税は、ますます国民に定着しています。私の知り合いは、トイレットペーパーなどの消耗品は、全てふるさと納税で手に入れているそうです。
商品のラインナップが広がり、日常生活必需品なども対象です。
そのうち、家電、車なども対象となるのでしょうか? さうがに、無理か。
空き家問題に新たな対策
2023/07/24 19:34:54
空き家問題に新たな対策
今や社会問題となっている空き家の管理強化や活用策を盛り込んだ改正空き家対策特別措置法がこのほど成立し、管理が行き届かない空き家については、固定資産税の優遇措置の対象から外すなどの措置が取られることになりました。改正法は今後、半年以内に施行される予定です。空き家対策をめぐっては、周知のとおり、空き家対策特別措置法が2015年に施行されて以来、放置すると倒壊のおそれがあるなど特に危険性が高い物件を「特定空き家」に指定し、自治体が強制的に撤去することが認められてきました。ところが、このような強制撤去は判断基準が明確でないことなどから十分には進まず、依然として空き家の増加に歯止めをかけるまでには至っていませんでした。このため、改正法では特定空き家になる前段階での対策強化が盛り込まれました。
具体的には、放置すれば特定空き家になるおそれがある物件を新たに「管理不全空き家」に指定し、市区町村が指導・勧告できる仕組みを導入しました。勧告等を受けても、なお状況が改善されない場合は、住宅用地の固定資産税を最大6分の1に軽減する特例措置が解除されることになります。従来は、空き家の状態でも住宅として固定資産税が減額されたため、その放置を助長しているとの指摘の声が聞かれていました。
広島県でも特に田舎に行くと、草ぼうぼうのなかに家がやっと建っている光景が見られます。跡継ぎの子が住まず、放置されています。台風で瓦など飛んで誰かに当たったら、大変です。相続の際、相続人間で「いらない」と言って、押し付けあうこともあるようです。背景には、人口減少などの要因があり、避けて通れない問題でもあります。財産的価値がなくさらに利益を生まないものを、どうするかです。国や地方自治体は、引き取っていただけるのでしょうか? 一筋縄ではいかない課題です。
公正取引委員会が初の注意勧告(免税事業者との価格交渉)
2023/06/26 09:18:17
公正取引委員会が初の注意勧告(免税事業者との価格交渉)
公正取引委員会はこのほど、同委員会ホームページのインボイス制度関連コーナーにおいて「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」と題する文書を公表しました。同委員会では令和4年1月(同年3月に改訂)、関係省庁と共同で作成した「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表して、独占禁止法・下請法上の考え方を明らかにしていますが、事業者に注意した事例を公表するのは今回が初めてです。注意事例によると、ある業界の発注事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められるにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、「インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げる」と文書により一方的に通告していたものです。業界も挙げており、イラスト制作業者が免税のイラストレーターのほか、農産物加工品製造販売業者が免税の農家、ハンドメイドショップ運営事業者が免税のハンドメイド作家、人材派遣業者が免税の翻訳者と通訳者、電子漫画配信取次サービス業者が免税の漫画作家に対しての5パターンを注意しました。
ポイントは2つです。上記Q&Aでも繰り返し指摘していたとおり、(1)取引先の免税事業者に対して、取引価格の引下げを文書で一方的に伝えていたことと、(2)経過措置期間は80%又は50%の仕入税額控除が認められるにもかかわらず、消費税相当額を取引価格から引き下げると通告している点です。
消費税の免税事業者は、先日ご紹介した内職の方のように、家庭の事情などを抱えておられる場合もあります。思い切った救助となる制度が導入されることを希望します。
孫への贈与による相続税への影響
2023/05/23 13:25:08
孫への贈与による相続税への影響
ひと頃、孫を養子にすると、(1)相続税の基礎控除額が増える、(2)法定相続人の増加によって累進税率が緩和される、(3)孫の時代の相続税負担を回避できる――などの理由から、いわゆる「孫養子縁組」が盛んに行われたことがあります。ただ、養子となった孫の相続税が2割加算の対象になってからは急速に萎んでいきましたが、最近、相続税対策として注目されているのが「孫への生前贈与」です。というのも、贈与税の基礎控除枠110万円を相続対策として活用する「暦年贈与」については、既にご承知のとおり、今年度改正で被相続人の生前に贈与された財産を相続財産に「持ち戻す」期間が3年間から7年間に拡大されましたが、相続人となっていない孫への贈与は相続税の課税対象とはならないからです。
この暦年贈与と並んで注目されているのが「相続時精算課税」です。これは2,500万円までの生前贈与が非課税となりますが、相続時に受贈財産を相続財産に持ち戻して課税するというもので、孫の場合は孫養子と同様に2割加算の対象となります。ところが、これについても今年度改正で年110万円の基礎控除が暦年贈与とは別枠で新設され、それ以下の贈与財産は相続財産に持ち戻されないことになりました。このため、孫持ちにとっては相続対策の手段が大幅に広がったといえそうですが、暦年贈与か相続時精算課税かは選択制ですので、どちらかを選ぶ必要があることから、慎重な判断が求められます。
相続税の節税については、いろんなアイデアが出ております。それを実行しても、裏目にでる場合もあります。じっくりと考えて、納得されてから行動されてください。
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
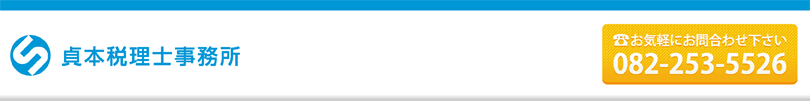



 RSS 2.0
RSS 2.0