税理士日記
税理士日記
相続時精算課税受贈者の権利義務は消息不明者も承継
2025/09/28 10:04:48
相続時精算課税受贈者の権利義務は消息不明者も承継
相続時精算課税により親から財産を贈与された子が、親よりも先に死亡しました。子には消息不明の配偶者がいましたが、その者は相続時精算課税の権利義務を承継するかが争われました。審判所は、配偶者は失踪宣告されない限り生存が推定されるため、権利義務は承継されると判断し、原処分庁の主張を認めていたことが分かりました(令和6年10月7日裁決)。同裁決によると、Aは平成24年、所有する土地・建物の2分の1を長女のBに相続時精算課税により贈与しました。ところがBは平成29年、Aの生前に死亡しました。なお、Bには平成4年当時に結婚した配偶者Cがいましたが、その後Cの消息は不明となりました。AとX(A・Bの養親)は令和元年にBの相続放棄を行いました。その翌年にAが死亡したため、XはAの相続に係る相続税の申告を行いました。令和5年、原処分庁は、CはBの相続人として相続時精算課税に係る権利義務を承継するにもかかわらず、Xの申告では相続税額の計算の基礎となる課税価格の合計額に贈与財産の価額が算入されていないとして更正処分を行いました。Xはこの処分を不服として審査請求しました。
Xは、Cが生存しBの相続人であることを原処分庁が立証していないことなどを主張しました。これに対し審判所は、Cは失踪宣告がされない限り生存が推定されると解するのが相当であり、CはBの相続人であったといえるから、Bの相続時精算課税に係る権利義務を承継し、贈与財産の価額はAに係る相続税の課税価格に加算されると判断、Xの審査請求を棄却しました。
相続時精算課税適用者(受贈者)が特定贈与者(贈与者)よりも先に亡くなると、相続時精算課税適用者の相続人は相続時精算課税の適用に伴う納税に係る権利義務を承継します。上記のケースは、一般の納税者の皆様には、思いつかないかもしれません。この制度を適用する際は、しっかりリスクを検討されてください。
コメント
コメントはありません
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
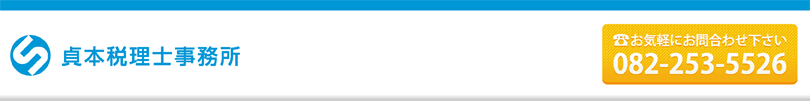



 RSS 2.0
RSS 2.0