税理士日記
税理士日記
マイナンバ−
2015/08/22 10:02:35
マイナンバ−
平成28年1月から制度の施行が予定されているマイナンバー制度。その番号の通知が、平成27年10月に開始されます。マイナンバー制度が開始されると、事業者は、社会保障や税の手続きのために、従業員やその家族のマイナンバーを取得し、適切に管理・保管しなければなりません。
今回は、マイナンバー制度の概要と税務関係書類等について確認し、個人情報の取扱いについて特例的な対応方法が認められる中小規模事業者についても確認しましょう。
【マイナンバー制度の目的】
マイナンバー制度は、いわゆる番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)に基づいて、マイナンバー(個人番号)を効率的に管理、運用することにより、「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」を目的としています。
ただし、マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きにしか使うことはできないとされています。
【税務関係の申告書等にマイナンバーを記載】
制度が施行されると税務関係の書類についてマイナンバーの記載が必要となり、例えば、申告書、申請書、届出書、法定調書等に提出する本人のマイナンバー、または法人番号を記載することになります。
給与所得の源泉徴収票や、給与支払報告書については、(1)支払者のマイナンバーまたは法人番号(2)支払いを受ける者のマイナンバー(3)控除対象配偶者および扶養親族のマイナンバー等を記載します。
【扶養控除等申告書に記載するマイナンバーの収集】
前述のとおり、番号が利用できる範囲は、法律や自治体の条例で定められた、社会保障・税・災害対策に制限されますが、事業主は、必要とされる従業員やその家族のマイナンバーを収集しなければなりません。
また、マイナンバーは、あくまでも番号法に規定されている事務処理のために、収集、管理されるものであり、事業主はその番号の管理を徹底することが求められます。
この点に関連して、番号の利用が開始される平成28年1月以前に、従業員からマイナンバーを収集することは可能なのかが問題視されましたが、内閣官房では、マイナンバー関係事務のために、あらかじめマイナンバーを収集することは可能であることを明らかにしています。
例えば、番号の通知が開始される平成27年10月以降、年末までの間に、従業員に平成28年分の扶養控除等申告書の提出を求める際、個人番号関係事務実施者となる事業主が従業員からマイナンバーを収集することは可能です。
【マイナンバー導入のためのチェックリスト】
現在、行政機関は、マイナンバー制度の周知に力を入れていますが、内閣官房では「マイナンバー導入チェックリスト」を公表しています。
そこでは、従業員数の少ない事業者(いわゆる中小規模事業者(事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者のうち一定の者を除く事業者))について、以下の内容について確認するよう周知が図られています。
○担当者の明確化と番号の取得
■マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人など)。
■マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。
■マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
(1)顔写真の付いている「個人番号カード」か、(2)10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。
○マイナンバーの管理・保管
■マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。
■パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。
■従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
○従業員の皆さんへの確認事項
■チェックリストの裏面「マイナンバー制度、はじまります。」を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。
まだまだ、どこまで徹底するのか、どのような取扱か、はっきりしないところもありますが、この時期に概要を知っておくことは大切です。準備しておきましょう。
遺言控除
2015/07/25 18:21:31
遺言控除を検討
自由民主党の政務調査会「家族の絆を守る特命委員会」で、「遺言控除」の導入が検討されました。提言されている「遺言控除」は、亡くなられた被相続人の遺言に基づいて相続がされた場合に、相続税の基礎控除に上乗せして一定額を控除する制度です。 「遺言控除」導入の目的は、遺言に基づく遺産分割を促進し遺産分割をめぐる紛争を抑止すること、また、介護による貢献に見合った遺産相続を促進することとされます。
委員会で示された資料によると、平成26年の遺言公正証書の作成件数は104,490件であり、前年の平成25年の96,020件より、8千件以上増加しています。
相続税制は、平成25年度の税制改正により、平成27年1月以降に発生した相続・遺贈から基礎控除が3,000万円+600万円×法定相続人数となり、改正前の6割に縮減されたことから、今後、相続税の申告は増加するとみられ、以前よりも相続にかかる関心は高まっています。
また、最高裁判所の司法統計年報によると、5,000万円以下の相続財産での争いが、相続財産をめぐる争いのおよそ75%を占めており、「遺言控除」が検討される背景には、相続財産をめぐる争いを防ぐ手立てとして、これまで以上に遺言の活用が期待されていることがあります。
委員会では、「遺言控除」のほか、現行の配偶者控除および配偶者特別控除に代えて、夫婦の世帯に対し、配偶者の収入にかかわらず適用される新たな控除である「夫婦控除」の創設も議論されており、「遺言控除」と同様、今後の税制改正での議論の行方が注目されます。
政策的に税制を作ることによって、相続争いはおさまるでしょうか? 税制って、コワイですね。
馬券の所得
2015/06/24 08:25:25
馬券の所得
いわゆる馬券の払戻金の取扱いをめぐる争い(刑事事件)で、最高裁が今年3月、馬券の払戻金が雑所得に該当する場合もある旨の最終判断を下したことを受け、国税庁はこのほど、一時所得を例示した所得税基本通達34−1を改正し、今後の取扱いを明らかにしました。改正通達は最高裁の判決内容に沿ったもので、これまで一時所得として取り扱ってきた競馬の馬券、競輪の車券の払戻金等から、「営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く」と明記しています。その上で、馬券を継続的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づき、インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして払戻金による多額の利益を上げ、一連の馬券購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨を、注書きに明示しました。つまり、これ以外はこれまでどおり、一時所得として取り扱われます。
今回の改正は法令解釈の変更に当たるため、同様のケースであれば、過納となっている所得税の還付請求が可能となります。ただ、その際には、最高裁判決と同様の購入行為の態様や規模等によるものである旨、また、外れ馬券に係る金額等が分かる書類の提出が求められます。この点にはくれぐれも留意すべきでしょう。
最近、度々、裁判所の判決で、税の取扱いが変わっています。税法改正の一つの方法を明示してくれています。
相続税の申告要非判定コ−ナ−
2015/05/27 09:29:03
相続税の申告要非判定コ−ナ−
国税庁は、平成27年1月の相続等から基礎控除額が減額されることによる相続税の課税対象者の増加に備え、「相続税の申告要否判定コーナー」を5月11日、ホームページ上に公開しました。既存の「確定申告書等作成コーナー」のようにインターネット上で自動計算できるシステムですが、遺産分割に左右される小規模宅地等特例や配偶者の税額軽減特例には対応していません。両特例の適用記載例は7月以降に公表を予定しています。国税庁が開発した判定コーナーは、相続財産の金額あるいは評価額などを入力することで、相続税の申告が必要か否かを大まかに判定できるものです。申告書の作成には結びつかないため、現時点では実務に直結するものではないですが、国税庁担当者によると、「「相続税についてのお尋ね」が届いた納税者は、このコーナーで計算した結果をプリントして税務署への回答に利用していただきたい」と補足する。
判定コーナーの手順を確認すると、(1)法定相続人の数を入力、(2)相続財産(土地等・建物・有価証券・現金・預貯金・生命保険金等・死亡退職金等・その他の財産・相続時精算課税適用財産)の金額等を入力、(3)債務及び葬式費用を入力、(4)相続開始前3年以内の贈与財産の金額等を入力――することで、自動的に加減算し、申告が必要かどうかの結果を示す仕組みです。
相続税がより身近になっていますね。
国外転出時課税
2015/04/24 09:57:10
国外転出時課税
国外転出時課税は平成27年度税制改正で創設された新制度ですが、平成27年7月1日以後に日本から国外転出等する場合に適用されます。1億円以上の有価証券や未決済の信用取引等を所有する場合に対象となるため、このほど公表された「国外転出時課税制度(FAQ)」において、その対象範囲を確認しておく必要があります。注意したいのは、文字どおりの国外転出は当然として、それ以外にも、国外に居住する親族(非居住者)へ対象となる資産を一部又は全部、贈与したり、相続・遺贈する場合も含まれる点です。非居住者への贈与であれば贈与者が含み益に対する所得税の確定申告をすることになり、非居住者が相続した場合は、国内居住者の相続人が含み益に対する所得税の準確定申告をする必要が出てきます(「FAQ」Q1)。
申告が必要となるのは、(1)国外転出時に対象となる資産を合計1億円以上保有し、かつ(2)国外転出の日前10年以内に国内在住期間が5年超――を満たすケース。外交等の在留資格に基づく在留期間は国内在住期間に含めません。対象資産に含み益があるか否かは、申告の有無に関係ないので注意したいです。対象資産は、有価証券や匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引等です(同Q3、4)。1億円以下か否かは国外転出時に評価して判定するが、平成27年12月末までは譲渡所得が非課税の国債や地方債も対象資産に含めて計算する点にも注意したいです。
国外に出国して悠々の老後計画などは、どうなるのでしょうか。
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
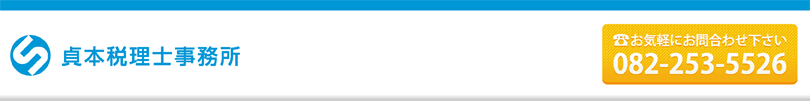



 RSS 2.0
RSS 2.0