税理士日記
税理士日記
借地権価額控除による貸宅地の評価
2018/03/22 19:52:37
借地権が設定されている土地の評価に当たり、不動産鑑定士による鑑定評価で算定した額は有効か否かが争われた事案で、東京地裁は、税務署長の主張する財産評価基本通達による評価を相当とし、納税者の訴えを棄却しました(平成29年3月3日判決)。
原告Xは、平成20年に死亡した被相続人の長男で、他の共同相続人らとともに複数の土地を相続しました。これらの各土地は借地権が設定された戸建住宅、賃貸住宅等の立ち並ぶ地域であったため、Xは不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、評価額を算定した上、相続税の当初申告を行いました。ところが所轄税務署長は、本件各土地について「評価通達によらない特別な事情があるとは認められない」として更正処分等を行いました。
Xは本件各土地について、ほとんどの土地は長期間借地契約が継続しており、建物も経済的耐用年数を超えているにもかかわらず建て替えられていないため、将来完全所有権に復帰する可能性が極めて低いと主張しました。これに対し東京地裁は、Xの主張する低廉な地代を基準とした収益価格による算定は相当でなく、評価通達25(貸宅地の評価)に定める借地権控除方式により算定された底地の評価が直ちに時価を超えることになるわけではないと示唆しました。本件各底地について、借地権価額控除方式によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められないと判断し、Xの主張を斥けました。
相続税や贈与税などの申告に際し、不動産鑑定士などの評価を用いる場合は、相当な注意が必要のようです。特別な事情の有無をしっかり判断することが安定安心につながります。
原告Xは、平成20年に死亡した被相続人の長男で、他の共同相続人らとともに複数の土地を相続しました。これらの各土地は借地権が設定された戸建住宅、賃貸住宅等の立ち並ぶ地域であったため、Xは不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、評価額を算定した上、相続税の当初申告を行いました。ところが所轄税務署長は、本件各土地について「評価通達によらない特別な事情があるとは認められない」として更正処分等を行いました。
Xは本件各土地について、ほとんどの土地は長期間借地契約が継続しており、建物も経済的耐用年数を超えているにもかかわらず建て替えられていないため、将来完全所有権に復帰する可能性が極めて低いと主張しました。これに対し東京地裁は、Xの主張する低廉な地代を基準とした収益価格による算定は相当でなく、評価通達25(貸宅地の評価)に定める借地権控除方式により算定された底地の評価が直ちに時価を超えることになるわけではないと示唆しました。本件各底地について、借地権価額控除方式によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められないと判断し、Xの主張を斥けました。
相続税や贈与税などの申告に際し、不動産鑑定士などの評価を用いる場合は、相当な注意が必要のようです。特別な事情の有無をしっかり判断することが安定安心につながります。
タクシー通勤
2018/02/23 18:22:43
過大通勤費 タクシー
通常必要と認められる通勤費の範囲を超える高額な出勤手当は、給与所得に該当するか否かをめぐる争いで、高松高裁は、納税者の請求を棄却した原審・高松地裁平成28年11月9日判決を支持、国側の処分を適法と認めました(平成29年6月27日判決)。同判決によると、病院を経営する医療法人Xは、同病院に勤務する非常勤医師や医療従事者に対して支払った往復交通費及び出勤手当について、税務当局から「出勤のために直接必要と認められる費用の範囲の金額を超えている」との指摘を受けました。その上で、当局は、直接必要な費用の範囲を超える部分は給与所得に該当し、源泉徴収の対象になるとして、Xに対して源泉所得税の納税告知処分等を行いました。
Xは、非常勤医師に対してタクシーでの出勤を前提として出勤手当を支給したと主張しましたが、高松高裁は「実際には、多くの非常勤医師等は自家用車や電車を利用してXに通勤していたことや、Xが非常勤医師に対して勤務地に設置されている駐車場の無料券を交付しており、大学病院から出勤する非常勤医師に対しては、そもそもタクシーの利用に関する説明をしていなかった」と認定しました。税務当局が本件出勤手当に係る非課税対象額の認定に当たって、公共交通機関又は自家用車を利用した場合に支給される金額を基礎として算定したことは不合理とはいえないとして、一審高松地裁に引き続き、Xの請求を棄却しました。
人手が足りず、お願いして来ていただく場合などでも、その方だけを優遇するわけにはいかないということです。広く皆に説明し、その上でリスクを覚悟して支給すべきですね。
医療費控除
2018/01/22 17:06:10
医療費控除の手続き
国税庁は、平成29年分所得税の確定申告から適用される医療費控除の明細書添付に当たっての質疑応答を「医療費控除に関する手続について(Q&A)」にまとめて公表しました。医療費控除については、セルフメディケーション税制の導入に伴う適用者数の増加に備え、領収書の添付又は提示から、領収書に基づいて必要事項を記載した医療費控除の明細書を申告書に添付する方法に改められました(質疑応答の問1)。ただし、経過措置があり、平成29年分から平成31年分までの3年間は、従来どおり領収書の添付等でも構いません。医療費の一部は明細書、残りは領収書という選択はできません(問2)。明細書の記載方法は問3。「医療を受けた方の氏名」や「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記載できます。
「おむつ使用証明書」などの証明書添付も簡略化されます。問4では、寝たきりの人のおむつ代について医療費控除を受ける例を挙げ、医師が発行した「おむつ使用証明書」などを添付等する必要がある場合は、(1)証明年月日、(2)証明書の名称及び(3)証明者の名称(医療機関名等)――を明細書の欄外余白に記載すれば、添付等を省略できます。
明細書以外にも、「医療費のお知らせ」、いわゆる医療費通知を添付等する場合も領収書の添付等が不要となります(問5)。必要となるのは、(1)被保険者等の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた者、(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称、(5)被保険者等が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称――の6項目を記載する医療費通知のみです。
問6以降にも医療費通知の取扱いなど、実務上重要な質疑が続いています。熟読が肝要です。
今までの手続きの方が、シンプルでわかりやすかったと思います。慣れれば簡単なのでしょうか。
新年 ご挨拶
2018/01/04 08:43:53
新年 ご挨拶
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。皆様のお役に立てるよう、一生懸命がんばります。貸金業者との和解が債務免除に該当(裁決)
2017/12/27 16:33:18
貸金業者との和解が債務免除に該当し、第二次納税義務へ(裁決)
貸金業者との和解が債務免除に該当し、第二次納税義務にあたるとした興味深い裁決をご紹介します。過払金の返還請求を受けた貸金業者が債務者と和解し、和解金を支払ったことが「債務免除」に当たるとして、第二次納税義務の対象となるか否かが争われていた審査請求事案で、国税不服審判所は「債務の免除を受けたと認められる」として、一部を除き納税者の請求を棄却しました(平成29年3月24日裁決)。
貸金業を営む請求人Xは、債務者Aとの間で金銭消費貸借取引を行いました。Aは本件取引に係る過払金の返還請求を行い、平成22年8月に和解が成立しました。Xは和解金をAに支払いました。平成27年、原処分庁はAの滞納国税を徴収するため、本件和解が国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に規定する債務免除に該当するとして、Xに対し第二次納税義務の納付告知処分を行いました。
Xは、本件和解は債務免除には当たらないとして審査請求しました。これに対し審判所は、「本件和解は、Aが和解金の支払を受けることを停止条件として、Xが負う過払金返還債務を免除する旨の合意を含む契約であり、このような契約による免除も国税徴収法39条の債務免除に含まれることは明らか」とした上で、和解金の支払が履行され、Xが実際に免除を受けた金額も確定できること等からすれば、本件和解による債務免除は、債務免除としての実質を有するものと評価でき、国税徴収法39条に規定する債務免除に該当すると判断しました。
これでは、こわくて貸金業者の方も和解できません。そのリスクも飲み込んで和解するということでしょうか。
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
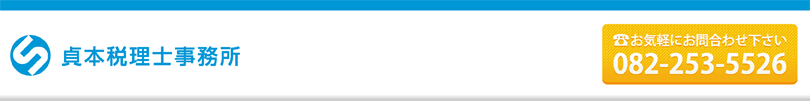



 RSS 2.0
RSS 2.0