税理士日記
税理士日記
物価高に対応した所得税の非課税限度額等を引上げへ
2025/12/26 16:32:37
与党、令和8年度税制改正大綱を取り纏め(2)
「インボイス経過措置は縮小したうえで延長〜与党、令和8年度税制改正大綱を取り纏め(1)」に続き、令和8年度税制改正大綱の特徴として、物価高を踏まえて、マイカー通勤の非課税限度額や深夜勤務の夜食代等の税法上、通達上の基準額の見直しがあります。マイカー通勤に係る通勤手当の非課税限度額は令和7年4月に遡及して年末調整で精算されますが、令和8年度税制改正では、通勤距離が片道65キロメートル以上を4つに細区分し、1万4,100円から最大3万4,800円の更なる引上げを実施します。さらに、マイカー通勤をしており、一定の要件を満たす駐車場等を利用、かつその料金を負担する者の1月当たりの非課税限度額が新設される。具体的には、マイカー通勤の通勤距離に応じた非課税限度額に、1月当たりの駐車場料金相当額を加算(5,000円を上限)します。
2つ目は、深夜勤務に伴う夜食代に係る非課税限度額の見直しです。現行、夜食代通達「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱い」により、深夜勤務者に対し、使用者に調理施設がない等の事情で夜食を現物支給するのが著しく困難な場合、1回の支給額が300円以下のものについては、所得税を非課税とする取扱いです。原則課税のところ、少額不追及・福利厚生の観点から、非課税とする運用ですが、昭和59年に1回200円以下から300円以下に上げて以来です。
令和8年度改正では、1回の支給額を2倍強の「650円以下」に引き上げて、所得税を非課税とします。
深夜勤務に伴う夜食代については、たまに税務調査で指摘されることがあります。経営者は、従業員によかれと思って、たびたび弁当などを出したところ、金額が多いとして給与認定されるというものです。何か切ない話です。もっと上げてもいいのではないでしょうか。
相続時精算課税受贈者の権利義務は消息不明者も承継
2025/09/28 10:04:48
相続時精算課税受贈者の権利義務は消息不明者も承継
相続時精算課税により親から財産を贈与された子が、親よりも先に死亡しました。子には消息不明の配偶者がいましたが、その者は相続時精算課税の権利義務を承継するかが争われました。審判所は、配偶者は失踪宣告されない限り生存が推定されるため、権利義務は承継されると判断し、原処分庁の主張を認めていたことが分かりました(令和6年10月7日裁決)。同裁決によると、Aは平成24年、所有する土地・建物の2分の1を長女のBに相続時精算課税により贈与しました。ところがBは平成29年、Aの生前に死亡しました。なお、Bには平成4年当時に結婚した配偶者Cがいましたが、その後Cの消息は不明となりました。AとX(A・Bの養親)は令和元年にBの相続放棄を行いました。その翌年にAが死亡したため、XはAの相続に係る相続税の申告を行いました。令和5年、原処分庁は、CはBの相続人として相続時精算課税に係る権利義務を承継するにもかかわらず、Xの申告では相続税額の計算の基礎となる課税価格の合計額に贈与財産の価額が算入されていないとして更正処分を行いました。Xはこの処分を不服として審査請求しました。
Xは、Cが生存しBの相続人であることを原処分庁が立証していないことなどを主張しました。これに対し審判所は、Cは失踪宣告がされない限り生存が推定されると解するのが相当であり、CはBの相続人であったといえるから、Bの相続時精算課税に係る権利義務を承継し、贈与財産の価額はAに係る相続税の課税価格に加算されると判断、Xの審査請求を棄却しました。
相続時精算課税適用者(受贈者)が特定贈与者(贈与者)よりも先に亡くなると、相続時精算課税適用者の相続人は相続時精算課税の適用に伴う納税に係る権利義務を承継します。上記のケースは、一般の納税者の皆様には、思いつかないかもしれません。この制度を適用する際は、しっかりリスクを検討されてください。
所得税の基礎控除の額の上乗せも含めて7年分年末調整から適用可
2025/05/14 15:42:22
基礎控除の額の上乗せも含めて7年分年末調整から可
「所得税法等の一部を改正する法律案」は、「7年度税制改正は衆院の迷走を経て、自公修正案が成立(TAXニュース2025年4月7日掲載)」のとおり、年度末ぎりぎりの本年3月31日に成立し、4月1日に施行されましたが、所得税の基礎控除の額の引上げは、令和7年分の適用に当たって、毎月の給与に係る源泉徴収からの適用は間に合わず、年末調整で精算する手続が必要となります。本年11月30日以前に出国するケースなど、年末調整で対応できない場合の適用関係も確認したいです。当初の基礎控除の額10万円引上げに加えて、与党が修正した年収200万です円以下の37万円上乗せと、年収850万円以下の4段階における上乗せ特例の適用は、いずれも令和7年分以後の所得税に適用されます。その適用に当たって確認したいのは経過措置で、令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年12月1日以後であるものについて適用され、同年11月30日以前のものは従前の取扱いとなります。昨年の定額減税が6月1日以後の給与から適用されたのとは異なり、基礎控除の額のアップは令和7年分の年末調整となります。
また、令和7年11月30日以前に、死亡した場合や出国をする場合の確定申告書を提出した者等に対する経過措置も設けられ、その申告書記載事項等について基礎控除の異動を生ずることとなったときは、同日から5年以内に、更正の請求をすることができる規定も設けられているので、注意したいところです。
何やら、複雑なことになっています。注意して処理されてください。
手形等のサイトが60日を超える親事業者に注意喚起
2024/12/26 17:52:27
手形等のサイトが60日を超える親事業者に注意喚起
中小企業庁及び公正取引委員会は先頃、手形等の手形期間又は決済期間が60日を超える手形等により下請代金を支払い、かつ現金払いへの変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した親事業者に、手形等のサイトを60日以内に短縮するよう注意喚起し、公表する取扱いを始めています。中小企業庁はこれまでも、手形や一括決済方式(ファクタリング等)、電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針により、下請法違反行為の未然防止を図ってきたところです。公正取引委員会も本年4月30日、業界の商慣行や近年の金融情勢等を総合的に勘案して、その指導基準等を変更しました。この変更に伴い、11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、60日を超えるサイトの手形等を交付した場合は、下請代金支払遅延等防止法の割引困難な手形の交付等に該当する恐れがあると判断し、このような親事業者には指導することを公表しています。具体的には、中小企業庁との連名で、9月27日付けでは約600者、さらに11月22日付けで新たに約100者に対して、手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いました。
中小企業庁及び公正取引委員は、今後も引き続き、中小事業者の取引条件の改善が図られるような取組みを進めていく意向です。
2026年に手形の廃止が予定されています。日本の企業において電子債権が当たり前の時代がやってきます。従前から習慣となった支払手段をいとも簡単に止めてしまうことは、驚きました。一方、下請保護の観点から手形のサイトを短くすることは、賛成です。中小企業が支払のために、債務を負ったり、手形を割り引くことが少なくなるならよいのですが・・・。
令和7年1月より申告書等への収受日付印押なつの廃止
2024/11/24 14:41:34
令和7年1月より申告書等への収受日付印押なつの廃止
国税庁は、「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」というホームページを更新しました。これは、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないという取扱の更新です。申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、納税者自身が控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするというものです。なお、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者に渡すそうです。この度、窓口用と郵送用のリーフレットが公開されました。申告書や届け出の名称などは、納税者がメモとして自ら記載する形式となっております。各種届出書などの記載には相当の注意を払う必要があると思います。例えば、消費税課税事業者届出書と消費税課税事業者選択届出書など内容が全く異なるもののメモ書きは要注意です。零細中小企業や個人の納税者・高齢者など税務に不慣れな方々に対する配慮を当局にお願いしたいです。
私は、記帳があまりできない納税者への記帳指導という仕事を長年やっておりました。多くの様々な納税者の皆様と汗をかきかき帳簿の記載方法・決算書や申告書の作成までお手伝いをさせていただきました。零細企業や個人とくに高齢者の皆様は後でeTaxで確認などできません。控えに日付印を押さないのであれば、せめて、税務署の担当者が届出書の名称くらいは記載していただきたいと思います。そのくらいの責任は負担していただけないでしょうか。
Page 1 / 66
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
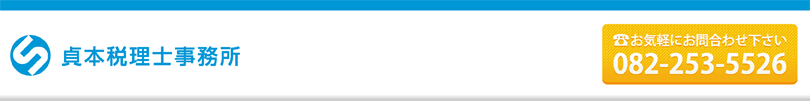



 RSS 2.0
RSS 2.0