税理士日記
税理士日記
固定資産税の過大賦課徴収
2017/05/23 09:05:01
固定資産税の過大賦課徴収の裁判例
土地に係る固定資産税の減額特例を適用せずに、自治体が誤って固定資産税を過大賦課徴収していた事案で、東京地裁は自治体側の責任を認め、国家賠償法上違法であると判断しました(平成28年10月26日判決)。原告の甲は所有する土地について、A都税事務所長から一般住宅用地等として固定資産税の税額の通知を受け、通知どおりの額を納付していました。甲は平成16年に本件土地上に建物を建築(不動産登記記録には「養護所」と記載)。
本来、それ以降本件土地は「小規模住宅用地」等として固定資産税の減額措置が適用されるはずであったものの、減額がされないまま過大な徴収が行われていました。甲から本件土地を相続した原告Xも同様に固定資産税を納付していましたが、平成26年10月ごろに、過大に徴収されていることが発覚しました。
裁判では、被告・A都税事務所長から還付を受けられなかった平成17年度分〜平成21年度分までの過納付金相当額の支払が求められました。東京地裁は、被告の国家賠償法上の違法の有無について、「被告評価担当職員は、小規模住宅用地の所有者からの申告の有無にかかわらず各要件の有無を調査し、特例が適用される土地にはその基準に従って算出した価格を評価すべき職務上の注意義務を負っている」と指摘しました。固定資産税の過大な賦課徴収行為は違法というべきと判断しました。
うーん、このような事例は、これから頻発するかもしれません。お役人のチェック機能が問われる状況です。過去の賦課を再確認する必要がありそうです。
ふるさと納税
2017/04/24 16:54:53
ふるさと納税の返礼品の上限の割合 3割へ
総務省は、ふるさと納税で過熱している地方団体間のいわゆる返礼品競争を緩和させるため、寄附金に対する返礼品の割合を3割以下とすることなどを求めた通知をこのほど、都道府県を通じて全国の地方団体に発出しました(総税市28号・平成29年4月1日付)。通知はまず、ふるさと納税の募集に関する基本的事項として「寄附を受ける地方団体は、返礼品の送付を強調してふるさと納税を募集することを慎む」ことを明示しました。大切なのは、寄附金の使用目的を地域の実情に応じて工夫することであり、このことを十分に周知して募集することを求めています。
重要なのは「返礼品のあり方」。「返礼品の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄附を募集する行為を行わないようにすること」としました。あくまでも寄附は無償の行為であることが基本であると強調しているといえ、「返礼品の価格」や寄附額の何%相当などといった「返礼品の価格の割合」を表示しないことを要求しています。このような考え方から、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品についても具体例をあげ、プリペイドカードや商品券などの金銭類似性の高いものや電子機器、家具など資産性の高いものなどは返礼品として送付しないとしています。また、寄附額に対する返礼品の割合の高いものも同様で、この割合の上限を「社会通念に照らし良識の範囲内のもの」として3割とすることも示しています。
返礼品を楽しみにされている皆さんには、冷水を浴びせられた感は、ありますよね。やはり、規制が入りました。
ふるさと納税は、返礼品によって、寄付をする自治体をえらんでいるのが実態です。 返礼品を扱う業者は、大儲けしているところもあると思います。業者の選定について、随意契約となっているか否かのチェックも必要ですね。やはり、元は自治体への寄付金ですから。
類似業種比準方式の見直し
2017/03/24 10:32:31
類似業種比準方式の見直し
平成29年度改正では、非上場株式の相続税評価における類似業種比準方式の見直しが行われます。国税庁の財産評価基本通達を見直すため、同庁は3月1日に改正案を公表し、同月30日までパブリックコメントに付しています。同方式の比準要素の見直しについて、1つは、上場企業の配当や利益、簿価純資産を「1対3対1」の割合で計算していたのを「1対1対1」に改めます(同通達180)。これにより利益の比重は5分の3から3分の1になるので、利益を出す成長企業の評価は下がり、一方で、純資産の比重が5分の1から3分の1と大きくなるため、内部留保の多い企業は評価が高くなる可能性があります。
2つ目は、上場企業において連結経営が進む状況を反映するため、連結財務諸表に基づく比準要素に改めます。
3つ目は、上場企業の類似業種株価について、前月、前々月、前々月の前月の中から最も小さいものと、前年平均の株価との選択制だったのを、「前2年平均」でも差し支えないとして(同182)、上場企業の株価が急上昇しても株価の影響を抑えるようにします。
4つ目は規模区分を見直し、大会社と中会社を拡大します(同通達178)。例えば、大会社の従業員数を100人以上から70人以上に下げるなどして大会社の範囲を拡大します。純資産価額との併用方式となる中会社については、中会社のなかの大中小を区分する総資産価額や取引金額を引き下げ、類似業種比準方式の割合が0.9と最も高い「中会社の大」の範囲を広げる見込みです。
相続税の財産評価においても、中小企業の内部留保に課税しようとする考え方が反映したものとなっているようです。その一方で、大会社の範囲を広げるなど世の中の現状に留意したものとなっているようです。
所得税の配偶者控除などの改正
2017/02/24 08:45:58
続々と税制改正
「所得税法等の一部を改正する等の法律案」が2月3日、開会中の第193回通常国会に提出されました。改正の目玉候補だった所得税改革は先送りされましたが、法人税関係ではデフレ脱却に向けての設備投資減税等の拡充にコーポレーガバナンスの視点が加わり、バラエティに富んだ改正メニューとなりました。国際課税の点からは、外国子会社合算税制の見直しに加え、相続税関係で納税義務の範囲の見直しが行われるので、留意したいです。所得税法改正案からみていくと、配偶者特別控除の見直しにより、配偶者控除が受けられる配偶者の収入制限は103万円から150万円に上がる一方で、新たに配偶者控除に所得制限(本人の合計所得金額が1,000万円以下)が加わります。注意したいのは、平成28年10月からの社会保険料の適用者拡大により、配偶者の社会保険料負担が発生すると、世帯の手取額が減り、配偶者の収入130万円の前後で逆転することです。平成30年分の所得税、平成31年度分の住民税から適用されます。
気をつけたい改正は、外国税額控除の適用を受ける場合にその基礎となる「控除対象外国所得税の額等」を納税者の立証すべき事項と明確化するものです。法人税法でも同様に明確化する条文に改められます。医療費控除は現行の領収書添付に代えて、医療費の明細書や医療保険者等の医療費通知書を添付すればよくなります。平成29年分から適用できるが、平成31年分までは現行との選択制としています。
いつの間にか、私たちの身の回りのルールが変わっていきます。追いつくのが大変です。順次、お知らせいたします。
相続税申告状況H27年相続開始
2017/01/26 13:57:06
平成27年分相続税申告事績
基礎控除引下げ等が行われた相続税改正の適用初年となる平成27年分相続税申告事績がさきごろ国税庁から公表されました。課税対象の被相続人割合(課税割合)は見直し検討時に想定されていた6%を大きく上回る8%となったことが分かりました。平成27年中に亡くなった被相続人数は、前年を1.4%上回る約129万人。うち、昨年10月末までの相続税額のある申告書提出に係る被相続人数は10万3,043人と前年分に比べ4万6,804人もの大幅な増加となりました。この結果、課税割合は4.4%から8%に上昇し、現在の課税方式になった昭和33年以降で最高を記録しました。基礎控除引下げによるところが大きく、課税価格1億円以下が前年分の1万4,846人から6万283人と約4万5千人も増加しています。なお、国税局別で見ると、東京国税局管内が7.5%から12.5%と2桁になったが、特に東京都は15.7%で、相続人の6〜7人に1人が課税対象となっています。
相続税申告に係る相続人の数も23万3,555人と前年分から10万人超増加し、相続税の課税価格は14兆5,554億円(対前年比26.8%増)、税額は1兆8,116億円(同30.3%増)と大幅に増えました。ただ、課税価格1億円以下が全体の約6割を占めるため、被相続人1人当たりの課税価格は1億4,126万円と30.8%も前年分を下回り、これに係る税額も28.9%少ない1,758万円で、平成6年以降では最低となりました。
基礎控除の引き下げは、従前の予測より大きなインパクトを与えていることが分かりました。税務署や税理士業界にも新たな対応が求められますね。
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
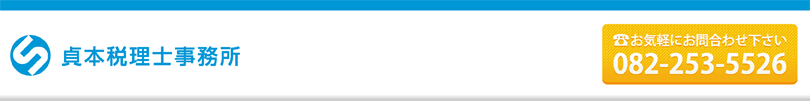



 RSS 2.0
RSS 2.0