税理士日記
税理士日記
平成29年度税制改正大綱の所得税
2016/12/21 09:51:46
平成29年度税制改正大綱の所得税
自由民主党・公明党は12月8日、平成29年度税制改正大綱を決定のうえ、これを公表しました。法人税改革に続いて、所得税改革の手始めに配偶者控除の抜本的見直しに挑みましたが、与党内の反発を受け、早々に断念したため、ほぼスケジュール通りの決着となりました。ただ、平成29年度大綱では所得税改革に今後も取り組む姿勢を示し、平成30年度税制改正においてゼロ税率の導入や税額控除への移行など控除方式のあり方に手を付けます。さらに、給与所得控除などの「所得の種類に応じた控除」と基礎控除などの「人的控除」のバランスを見直すとしており、後者の比重を高めることが予測されます。
平成29年度改正で実施される配偶者控除の見直しを確認すると、納税者本人の所得制限が初めて設けられ、所得金額に応じた控除額は、(1)900万円以下なら38万円(住民税は33万円)、(2)900万円超950万円以下なら26万円(住民税は22万円)、(3)950万円超1,000万円以下なら13万円(住民税は11万円)と逓減していく仕組みとなります。配偶者特別控除については、その対象となる配偶者の合計所得金額の下限は38万円超のままだが、上限を76万円未満から123万円以下へと広げる。この結果、配偶者控除を受けることができる控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者の合計所得金額は103万円から150万円に広がる。平成30年分以後の所得税、平成31年度分以後の個人住民税から適用されます。
配偶者控除に納税者本人の所得制限を設けるそうです。所得税の確定申告の際、計算が複雑となります。もっとシンプルにしていただけないでしょうか。
所得税と消費税の税務調査状況
2016/11/22 17:34:19
所得税と消費税の税務調査状況
国税庁は、「平成27事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」を公表しています。それによると、平成27事務年度(平成27年7月〜平成28年6月)に行われた所得税の実地調査の件数は、特別調査・一般調査が4万8千件(前事務年度4万9千件)、着眼調査が1万8千件(前事務年度1万8千件)、簡易な接触の件数は58万4千件(前事務年度67万2千件)となっています。
これら所得税の調査等の合計件数は65万件(前事務年度74万件)で、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は39万6千件(前事務年度46万6千件)、申告漏れ所得金額は合計で8,785億円(前事務年度8,659億円)となっています。
また、事業所得を有する者の1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な業種は下記のとおり(カッコ内の金額は1件あたりの申告漏れ所得金額)。
1位 キャバレー (2,628万円)
2位 風俗業 (2,326万円)
3位 畜産農業(肉用牛) (1,471万円)
一方、消費税(個人事業者)の実地調査の件数は、特別調査・一般調査は2万7千件(前事務年度2万8千件)、着眼調査は8千件(前事務年度8千件)、簡易な接触の件数は5万3千件(前事務年度5万件)となっています。
これら消費税(個人事業者)の調査等の合計件数は8万8千件(前事務年度8万6千件)で、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は6万1千件(前事務年度5万9千件)、調査による追徴税額は合計で271億円(前事務年度232億円)となっています。
このほか公表資料では、参考資料として下記の4項目が取り上げられており、調査が強化されていることをうかがわせます。
・いわゆる「富裕層」への対応
・海外投資等を行っている者の調査状況
・無申告者に対する調査状況
・インターネット取引を行っている者の調査状況
近年、税務署の職員数が以前より少なくなっていると思われます。よって、税務調査もより効率を求められています。しかし、手続きに時間がかかり、最終的な調査期間は伸びているように感じます。皆さん、お金を儲けて、適正申告しましょう。そうしたら、税務調査もこわくないですよ。
被相続人のマイナンバー
2016/10/22 16:03:15
相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載不要
国税庁は、平成28年10月以降に提出する相続税の申告書について、被相続人(亡くなられた方)の個人番号(マイナンバー)の記載を不要とすることを同庁のwebサイトに公表しています。社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入された平成28年1月1日以降、相続または遺贈(贈与した者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により取得する財産にかかる相続税の申告書には、被相続人の個人番号を記載することとされていました。
国税庁によると、相続税の申告書に被相続人の個人番号を記載することについては、納税者から、
・故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税の申告書に被相続人の個人番号を記載することは困難
・相続開始前に、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある
といった趣旨の意見が寄せられていました。
国税庁では、これらの意見を踏まえ、関係省庁と協議・検討を行い、被相続人の個人番号を記載することは困難であり、生前に個人番号の提供を受けることには抵抗があることから、安全管理措置等に関する負担を考慮したうえで、相続税の申告書に被相続人の個人番号を記載することは不要とすることとしたとしています。
また、この取扱いの変更にかかり、相続税の申告書は様式が改訂されています。
なお、相続税の申告書を提出する際には、申告書に記載されている各相続人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。
マイナンバーは、原則として、他人に見せてはいけないとすれば、実務上当然ですね。 また、相続開始前の親族の心情を配慮しても、当然でしょう。
配偶者控除の見直し
2016/09/23 15:21:01
配偶者控除の見直し 平成29年度改正の方向性
実効税率20%台を実現した法人税改革に代わり、長年の課題だった配偶者控除見直しを含む所得税改革が、29年度税制改正の主要課題になる見込みです。9月9日の第1回政府税調で議論の口火が切られ、間もなく与党税調でも各府省庁からの要望項目の検討が始まりますが、盤石な与党体制が実現した今、29年度税制改正大綱では、主要課題の所得税改革についても何らかの改正案や方向性が示される可能性が高いです。配偶者控除見直しは、これまで政府税調が議論をリードしてきました。26年11月時点で廃止を含む5つの選択肢が示されましたが、消費増税を前に所得税でも増税する案は打ち出せず、先送りとなりました。だが、ここに来て、女性活躍を推進する政府の方針を追い風に、パートが就労調整する「103万円の壁」をなくすための見直し論が浮上しています。
5つの案の中では、単純に増税する廃止案は現実的ではなく、(1)配偶者の所得計算で控除しきれなかった基礎控除を、納税者本人に移転する「移転的基礎控除」と、(2)夫婦世帯を対象とする夫婦控除が検討される見込みです。2つの比較では、パート世帯が増税となるほか、配偶者の税率が低い場合、配偶者が基礎控除を受けるより納税者本人が移転的基礎控除を受けるほうが有利となり、配偶者の就労を抑制する(1)より、配偶者の収入に関係せず、働き方の選択に中立的な(2)の夫婦控除が有力です。ただし、個人単位の課税から世帯単位への課税に舵を切ることにもなりかねず、所得税全体で丁寧な議論を積み重ねることが望まれます。
配偶者控除が改正されると、国民の生活スタイルや家族のあり方まで影響がでそうです。 遺言の相続税の減税もそうですが、日本人の昔ながらのそしてプライベ−トな所を、税金というお金勘定で左右することに、不安を抱きます。
しっかりした議論が必要ですね。
民法(相続関係)等の改正に関する中間試案
2016/08/22 15:10:39
相続関係の民法等改正の中間試案のパブリックコメント
法務省はこのほど、法制審議会民法(相続関係)部会がまとめた「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」をパブリックコメントに付し、9月30日まで意見募集しています。中間試案のうち遺産分割をみると、配偶者の相続分の見直しの方向性として、一つは被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やす案です。婚姻後増加額(遺産から被相続人の婚姻時の財産を控除した額)には配偶者の貢献が高いとみて法定相続分より高い割合を乗じる一方、遺産から婚姻後増加額を控除した額には法定相続分より低い割合を乗じて、両者を足した額が現行の配偶者の具体的相続分を超える場合には、配偶者の申立てにより、その超過分を配偶者の具体的相続分に加算できるというものです。
もう一つは、婚姻成立後、20年又は30年経過した場合に、(1)一定の要件(例えば当該夫婦の届出)のもとで、又は(2)自動的に法定相続分を増やすという案です。具体的な増加後の法定相続分は、子及び配偶者が相続人であるときは配偶者の相続分を「3分の2」、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは配偶者の相続分を「4分の3」、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者の相続分を「5分の4」に増やすものです。
その他、自筆証書遺言の方式緩和として、財産の特定事項は自書でなくてもよいとすることや、相続人以外の者が被相続人の療養看護等を行った場合に一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求することができるようにするなども盛り込まれています。
相続関係の民法等の改正は、みなさんの生活に直結します。 注視していきましょう。
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
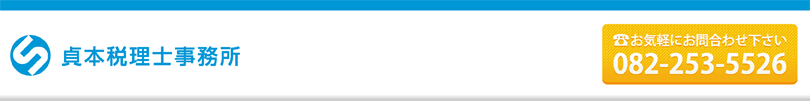



 RSS 2.0
RSS 2.0